ジャンパー線支持に高圧ピンがいしを使った旧式については、神奈川県相模原方面でも、今もなお、それなりに目にすることがあるが、ここは中でも近代設備っぽいような形での発見となった。
架空地線キャップを被せたもので、3本のジャンパー線支持に高圧ピンがいしという構成は、それほどは見かけまい。w
架空地線の支持は、鳥居型である例が多そうだ。
3歳の頃から電力会社の配電線に興味があり、個人的に気になったものや変わったものなどを巡っています。 ※当サイト内の画像・文章の転載、複製、改変等は一切禁止します。もし発見した際は、警告のうえ、悪質な場合には法的措置をとる場合があります。 当サイトは、電力会社や機器メーカー等とは一切関係ありません。 Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.
ジャンパー線支持に高圧ピンがいしを使った旧式については、神奈川県相模原方面でも、今もなお、それなりに目にすることがあるが、ここは中でも近代設備っぽいような形での発見となった。
架空地線キャップを被せたもので、3本のジャンパー線支持に高圧ピンがいしという構成は、それほどは見かけまい。w
架空地線の支持は、鳥居型である例が多そうだ。
実はこれ、以前は高圧ピンがいしだったのである。
まぁ今じゃ、新種や設備更新後の設備(旧式の既設設備に後付け例もあり)では、どこでも限流ホーン付きのクランプがいしを取り付ける傾向にあるから、別に不思議ではないか
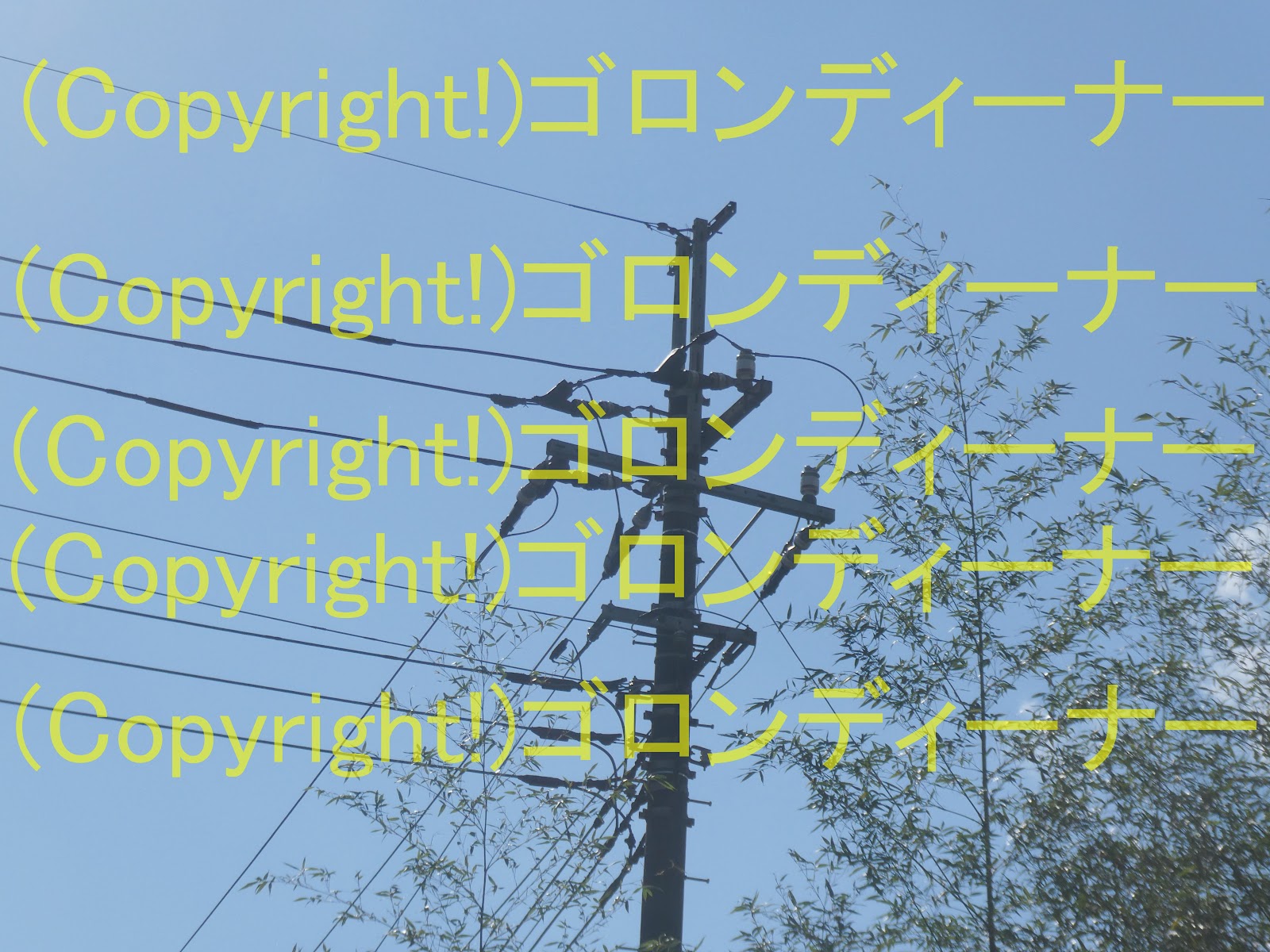 |
| ちなみに2010年には、ぼっとん便所の塩ビ管の突き出た長屋まであったらしい。今回撮影のものは、2010年には見つけていたものだった。中々行ける機会がなく、14年越しの撮影となったのだった。w鳥居型と古い長屋の構成がよかったのにな~ |
続いて終端方面の隣接設備の振り分け引き留め柱は、ジャンパー線支持は10号中実がいしである。
こちらも以前は高圧ピンがいしだったらしいが、クランプがいしでなく10号にしたみたいだ。
ちなみにこの配電線の横側には・・・
谷や川を超える区間では、スパンがそれなりに長くなるから、支持物も頑丈そうに2本建柱するわけだが(それをH柱という)、ここは手前の1本は途中で設備更新されたのだろうか、少し新しい感じの柱に思える。
なお、各柱は内側になるようにして、若干傾かせているようである。
ちなみにこの後は、廃墟マニアで有名な、相模湖ローヤルA館の目の前の道を通るようである。(通行止め)
再び国道20号に合流した付近で、三相だった高圧配電線は単相となる。
前のページのすぐ付近では、そういったものも見つかった。
木製電柱の場合、以前は直接、柱に釘などを打って、低圧ラックを固定していた。
斜めに切られた支柱部分には、かさ金なし。
年式は1965年(昭和40年)のようである。
少し前まではジャンパー線支持は高圧ピンがいしだったようだが、撮影に来た時にはもう既に、真新しい10号中実がいしへ取り換えられていた。
しかし取り換え後も、以前使われていた高圧ピンがいしは残り続けたようで、両側にそれがあるのが見て取れる。
外せないのは、降圧耐張がいしのストラップと重ね付けされているからである。