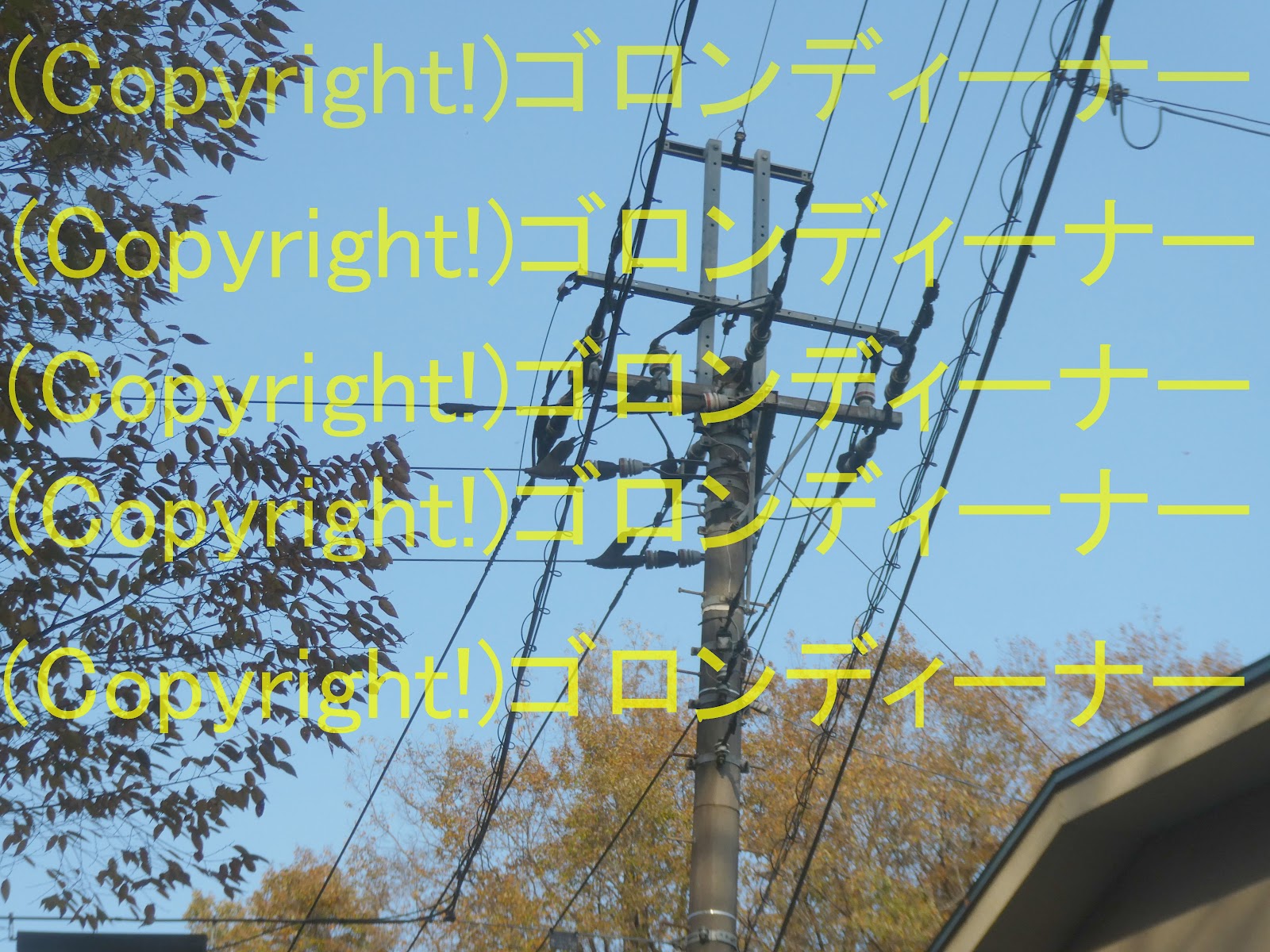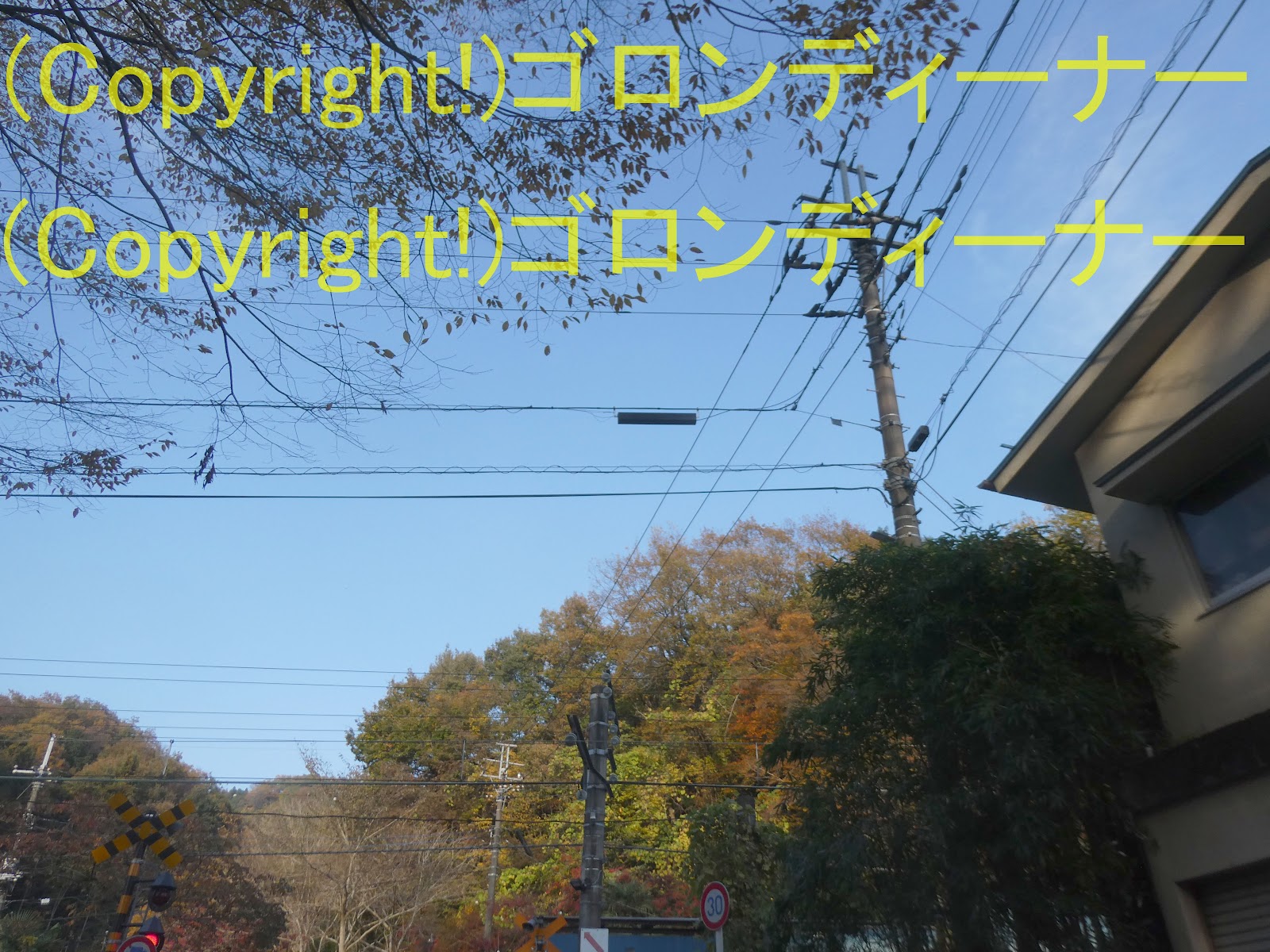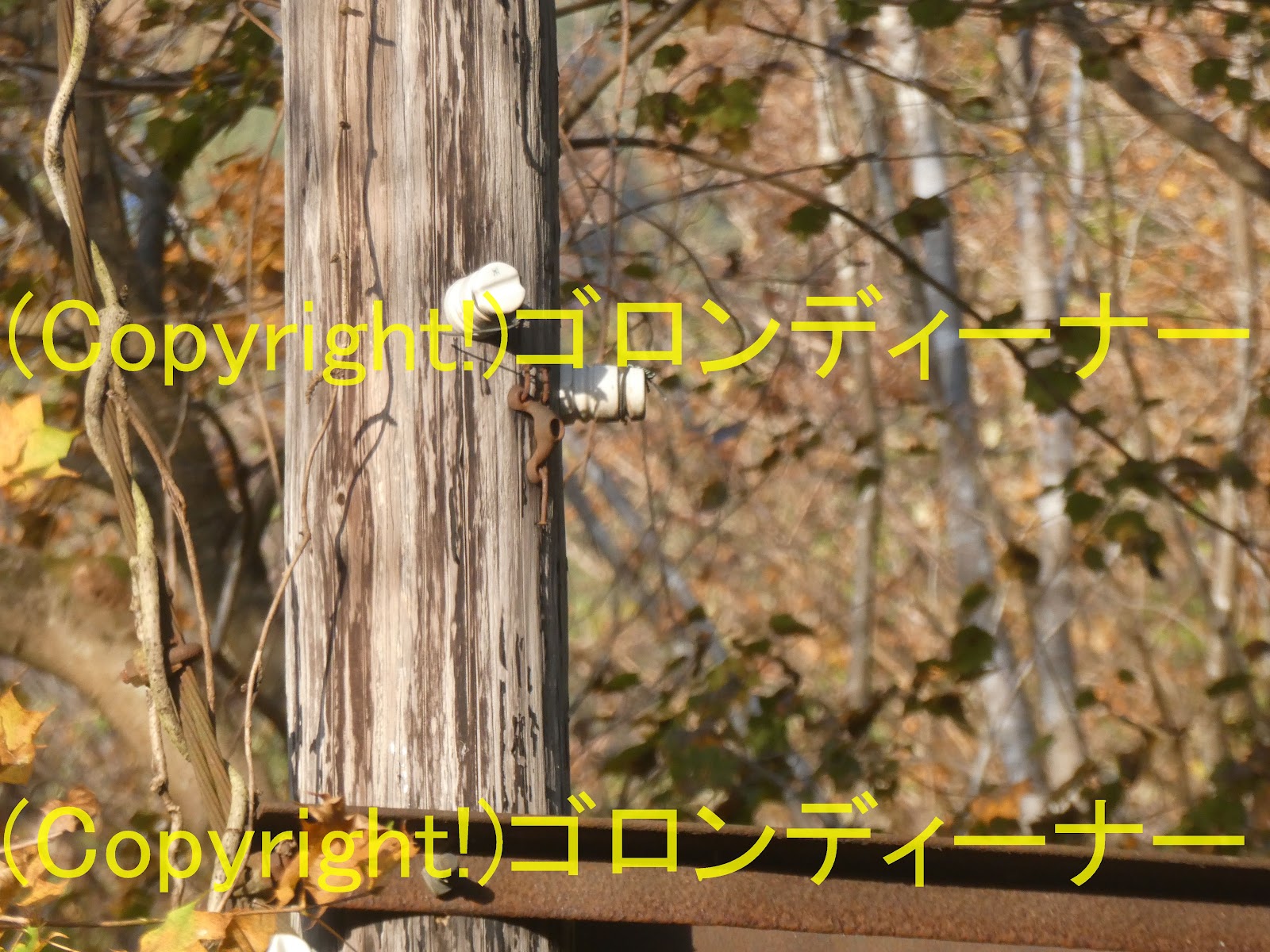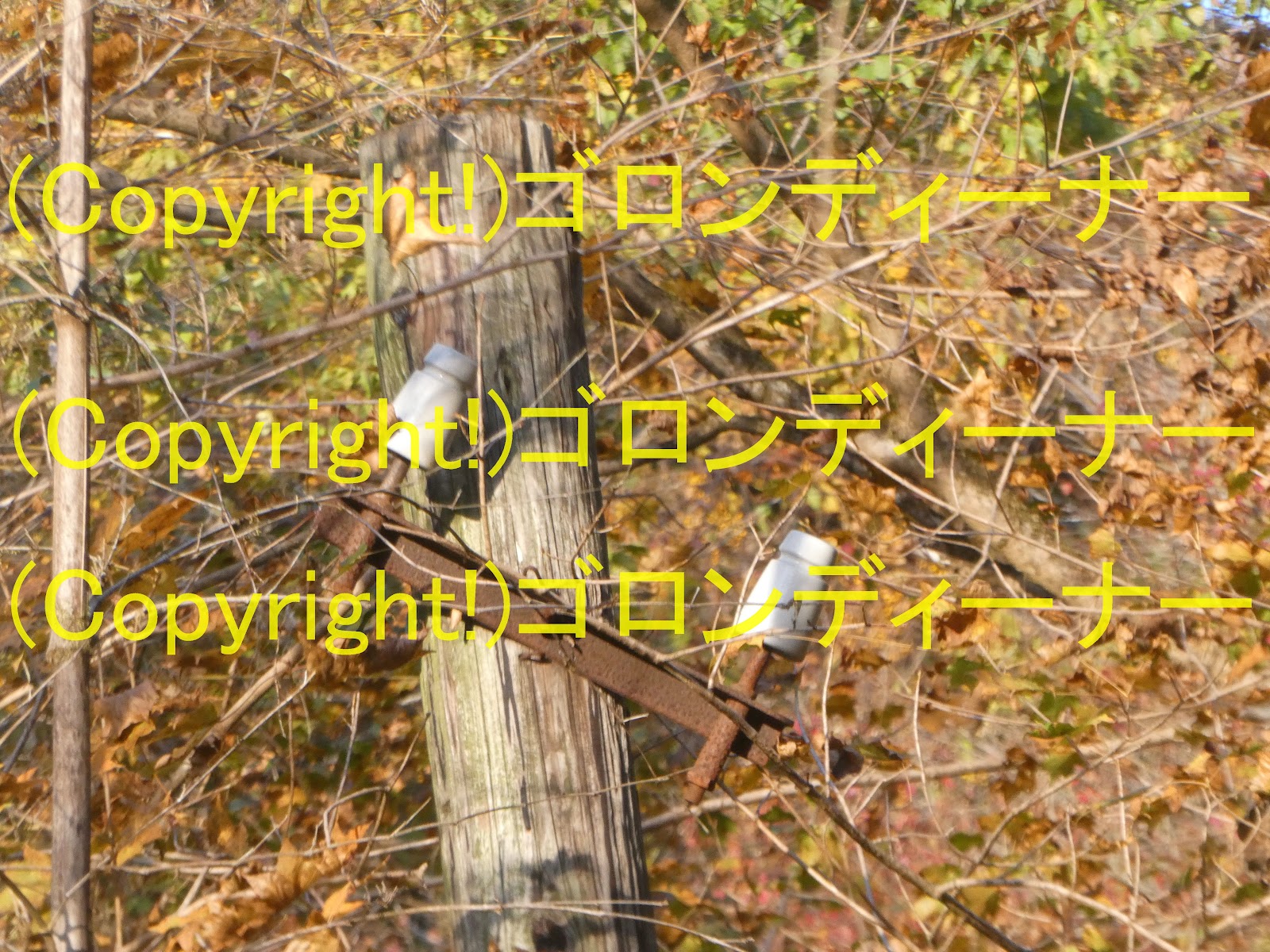こちらはまたもや鳥居型バージョンで発見!
丁度電車が通ってきた。
これは横断後にあるもの
<おまけ>
この奥の方には、木柱を使用した謎の廃線も!
低圧2重がいしかな、こりゃ?それが付いているアームも古く、アングルである。
下の方には井形がいしも
最近ではこれは、玉がいしであることが多い。
どうやらここには以前、鉄道の線路があったらしい。
ボロボロとなった線路が見えてきた。
さらに進むと鉄道の架線柱が見えたが
これは分割がいし、いや、主にそれは内線で使われていたであろう、特カップがいしだな。
本来の用途としては、それは屋内用である。
架線を支えていた懸垂がいしは、180mmと思われる。
架線は断線しながら残っている感じか
アングルには傾斜もみられ、だいぶ老朽化が進んでいそうだ。
そのままではアングルごと落下するであろう。
取り付け部が特に腐りやすい。
これは転轍機か